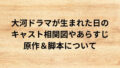子どもの頃は豆まきをして、鬼を払う行事として慣れ親しんできた節分について、調べ簡単にまとめたことを紹介していきます。
節分とはどんな行事?
節分とは、読んで字のごとく、「季節を分ける」という意味になります。
太陽暦では立春に最も近い新月の日を元日とし、その日を立春として考えました。その立春の初めの日を新年の日とし、その前日を大みそかとして、その日に邪気を追い払い、良い新年を迎えるための準備の日ということになりました。
節分の由来は?
節分は、旧暦の立春が新年であったため、その前の日に邪気を払う目的ではじまったのが由来とされており、現在の大みそかのような日であったといわれています。 年の変わり目に邪気を払い、1年の無病息災を願う行事として豆まきをおこなったり、恵方巻を食べる習慣が残っています。
節分を英語でどういうの?
日本にしかない行事なので英語にする時も日本名のままで問題ないようです。しかし、節分のことを英語ではこのように説明するといいようです。
"Setsubun" means the day between two seasons.
節分は二つの季節の分かれ目という意味です。
また簡単ではありますが、どのようなことをするのかを説明すればいいのではないかと思います。
People throw beans to expel evil spirits and bring in good luck.
邪気をはらい、福を呼び込むために豆まきをします。
このように説明すれば、より理解できるのではないかと思います。
豆まきの意味は?
宮中で節分に行われていた「追儺(ついな)」という鬼払いの儀式が広まったもので、季節の変わり目に起こりがちな病気や災害を鬼に見立て、それを追い払う儀式として行われていました。 昔から節分には厄を払い新年の幸せを願う行事が日本各地で行われ、現在も習慣として行われています。
恵方巻とは?
恵方巻とは 邪気が入り込みやすい季節の変わり目の節分の日にその年の福を司る歳徳神(としとくじん)がいるとされる吉方位恵方を向いて食べると縁起が良いとされる太巻き寿司のことです。
その太巻きの具材は、七福神にちなんで、7種類の具材がよいとされていますが、決まりはありませんので、好きな具材で作ってもいいと思います。
食べるときには、恵方巻きは切り分けず、長い1本のまま丸かぶりします。できれば最後まで無言のまま1本食べきりましょう。切り分けたり、途中で食べるのをやめるのは「縁が切れる」と言われています。また、無言で食べることは「福が口から逃げない」という意味があるようです。
まとめ
冬と春の季節を分けることとして、昔ながら習慣として大切に残っている節分。意味を知って、古来より受け継がれた日本文化を大切に残していければと思います。